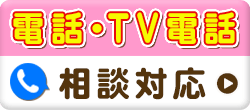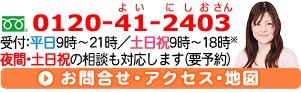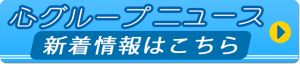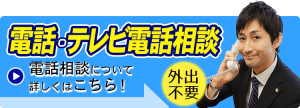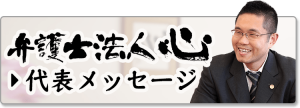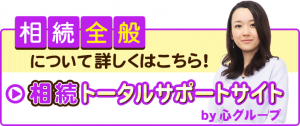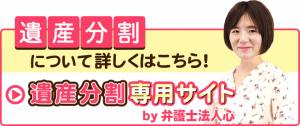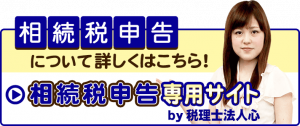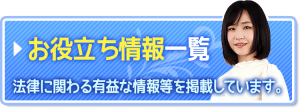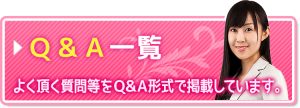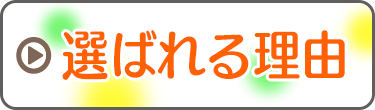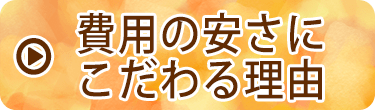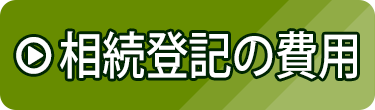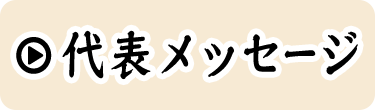未登記の建物を相続した場合の手続き
1 登記がされていない建物の存在
建物は、原則として、法務局での登記がされています。
不動産登記法では、建物を新築したときには、その所有権を取得したときから1か月以内に建物の表題登記をすることが義務付けられています。
そのため、相続財産に建物がある場合にも、登記がされていることが通常ではあるのですが、なんらかの事情によって、建物が登記されていないこともあります。
そのような建物を未登記の建物と呼びます。
2 登記の手続き
建物については、すでに建築されている建物を、表題部の登記と、相続で取得した相続人名義での保存登記をする必要があります。
実際には、未登記の建物について、この手続きをされない方も多いように思われますが、この義務の違反については、10万円以下の過料という罰則も規定されていますので、注意が必要です。
法律上は登記の義務がありますし、この登記の手続きをしておかなければ、基本的に、この建物を売却などの処分の対象とすることや、担保の対象とすることもできません。
3 課税台帳の変更手続
未登記の相続財産の建物であっても、通常、自治体の課税台帳には所有者が被相続人として登録されており、固定資産税の課税もされています。
相続で建物を取得する者が決まった場合には、自治体にその内容で所有者変更届を提出し、その後の課税対象者を変更する手続きをする必要があります。
具体的に提出する書類と手続きの内容は、各自治体のホームページで案内されており、書式もありますので、それに従って手続きをされてください。
通常は、この手続きには、法務局で必要とされる書類と同様の書類が必要になります。
すなわち、申請書に加えて、相続人関係のわかる戸籍、遺産分割協議書(申請書自体に相続人の実印を記載する体裁のものもあります)、印鑑登録証明書が必要になります。
なお、登記されている建物は、名義変更登記をすれば自動的に課税台帳の所有者も変更されますので、この手続きは必要ありません。